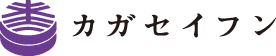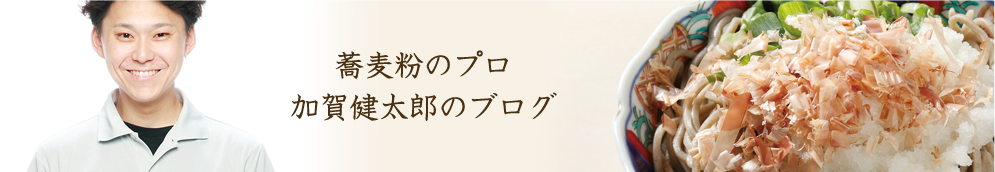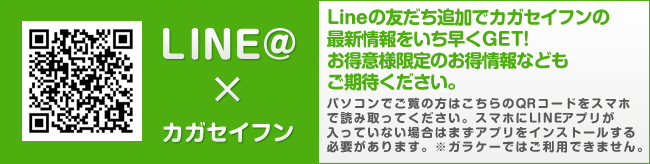福井市片町のル・リアン(Le Lien)で行われたフレンチ蕎麦会に参加させていただきました。今回のお料理には全てソバが使われているというからとても楽しみにしていました。
シェフの北野さんはフランス料理にソバは良く使用される食材だからそば処福井のそば粉を使った料理はお店のメニューに加えたいと考えていたそうです。しかし、福井でお店を開いてから何度か地のそば粉を使って料理したみたものの色味や食感など目指す仕上がりにならなかった。その後もチャレンジしてみたけどあまり変わらない。修行先ではそんなことにはならなかったのに福井で同じようにいかないのは自分の料理の仕方に問題があるのか、それともそば粉に問題があるのか、やればやるほどどこに理由があるのか分からなくなっていたそうです。
そこで事前にどういった料理をどういった形で提供するのか、またどのような仕上がり(食感、色味、香り)を求めているのかをお話させていただたところ「そば料理の為のそば粉選び4つのポイント(下段で説明します)」がわかりました。それを元に今回はメニューに適した相性の良いそば粉をそれぞれご提案させていただきました。
そばがきというと出汁とか塩、醤油とワサビなど一般的にはシンプルに食べますけど、このコンソメでいただくのも美味しいです。そばがきは完全に和風なのにコンソメに沈めただけでフレンチの香りがする。レフォールの香りも効いて気持ちのいい一品でした。
 ▲自家製スモークサーモンのサラダ 蕎麦粉のピタパンに挟んだケバブスタイル
▲自家製スモークサーモンのサラダ 蕎麦粉のピタパンに挟んだケバブスタイル
自分のスモークサーモンを作るため道具まで手作りして作っているというスモークサーモンは、フレッシュなサーモンの香りとほのかなスモーク香の塩梅が良くていつもでも噛んでいたくなるほど味わい深い。ムチムチっとしたソバのピタパンとも良く合って焦げ目のカリッとしたところが美味しい。
とても薄く焼かれたそば粉のガレットに厚切りベーコンと卵、チーズ、粒こしょう。
卵がかたよって仕上がられているので、生地のパリパリ感、卵との組み合わせ、ベーコンと一緒に、全部からめて・・と一皿でいろいろな楽しみ方ができる。フレンチシェフが作るガレットは生地自体はもちろんのこと、中に加える具材も一つ一つ細かく手が加えてあるので、味を確かめながらいただきました。
コースの途中、シェフの北野さんから今回のそば料理について説明があり、僕も今回のそば粉について少しお話をさせていただきました。
 ▲フランス産鶉(うずら)のロースト 蕎麦の実ファルシー 大野産有機野菜 鶉のジュのソース
▲フランス産鶉(うずら)のロースト 蕎麦の実ファルシー 大野産有機野菜 鶉のジュのソース
鶉をいただくのは人生始めてか、2回目だと思います。
表面の皮がこんがりパリッと焼けた鶉は香ばしいお肉の良い香りがします。そのままかぶりつけるようにと丁寧に骨抜きされた鶉を二つに切るとぎっしりとソバの実が詰まっていました。
ソバの実だけだとボソボソと食感があまり良いものではなかったりしますが、この蕎麦の実はあらかじめコンソメでリゾット風に仕立ててあるそうで、鶉から出る脂でしっとり感とコクが出ています。
粗挽きそば粉を使ったパンの上にソバの実が散らしてあります。
パンを二つに割くと中に閉じ込められたそば粉の香ばしい香りが一気に広がり、小麦粉とはまた違った穀物の甘い香りが立ち上ります。ナッツのような食感の蕎麦の実がアクセントになって鶉のジュのソースにたっぷり浸して食べればたまりません。
今回の〆。北野さんが日本蕎麦をフレンチスタイルで食べてもらうと言っていたお料理。
フォアグラにあまりなじみが無いのですが、それをムース状に出汁に溶かしていただくというお蕎麦はさっぱりした汁に濃厚なムースが入ることによって複雑な味わいの出汁に変わりました。蕎麦はちょっと出汁につけるくらいにして蕎麦の香りとフォアグラの脂濃さを楽しみます。お蕎麦は、仕込みの合間に弊社にお越しいただき、その場で挽いたそば粉を使って打った手打ちそばです。一本一本丁寧に打ったお蕎麦はコシがあって美味しかったです。
 ▲大野産オーガニックルバーブを使った蕎麦粉のクラフティ 花垣大吟醸酒粕アイス添え 自家製ジンジャーピュレ
▲大野産オーガニックルバーブを使った蕎麦粉のクラフティ 花垣大吟醸酒粕アイス添え 自家製ジンジャーピュレ
下層のそば生地とルバーブの食感がおもしろい。男性には少々甘いんですが、さらっと食べられてしまうのはこの食感の妙があるからでしょうか。
 ▲入り立てそば茶と蕎麦の実と蕎麦粉を使ったフロランタン フランスルビュイ産レンズ豆の粒あんを混ぜて
▲入り立てそば茶と蕎麦の実と蕎麦粉を使ったフロランタン フランスルビュイ産レンズ豆の粒あんを混ぜて
ローストの加減が難しいと言っていたそば茶。
蕎麦の実を北野さん自らローストし、絶妙なタイミングで淹れたそば茶は、まるで経験があるかのような見事な仕上がり具合で驚きました。さすがプロだなぁと感じます。クラフティで口の中が甘くなっていたからそば茶がさらに美味しかったし、今度は甘さ控えめのフロランタンが良かったです。
そば料理の為のそば粉選び4つのポイント
①作りたい料理とソバの「品種」の特徴が合っているか
穀物や野菜に限らずソバにも「品種」があります。日本国内には北海度のキタワセ種、長野県の信濃1号(2号)、茨城の常陸秋そばを始め、島根県の横田小ソバ、長野県の奈川在来など昔からの在来種も数多く存在します。この品種は種類によって特徴があり、挽き方にもよりますが味も食感も異なります。どうやってもパリパリにならず、モチモチ感や生焼けのようなぬめりが際立ってしまう場合は粘りの強い品種なのかもしれません。
②作りたい料理と「挽き方」で変わるそば粉の特徴が合っているか
日本ではソバの香りや味を重視するのでつなぎ2割の二八そばや十割そばが好まれます。少ない小麦粉の量でそば粉を繋ぐ必要があるので石臼を使いじっくり丁寧に粘りを引き出すようにそば粉を挽きますが、ヨーロッパではそこまで重視しないので石臼と言っても日本ほど手の込んだものではなく、あくまで粉にするという程度のもの。粘りが無くサラサラした仕上がりになりますが、これがガレットや料理に使う場合にはいい効果が出るのでしょう。黒い白いなどの色味の違いもこの挽き方によります。皮ごと挽けば黒っぽくなりますし、皮を剥いて挽けば白っぽくなります。
③作りたい料理と蕎麦粉の「相性による使い分け」ができているか
品種と挽き方によっていろんな個性を持つそば粉は、どういう料理でどういう仕上がりを求めるかによってタイプを選び、調理法や他の素材との組み合わせを考える必要があります。全く性格の違うそば粉を2種類用意されて双方をブレンドしてみるのも面白いかと思います。
④そば粉のプロが料理人にいかにそば粉を提案してくれるか
福井県産そば粉(福井在来種)は粘りの強い品種です。日本では生そばで食べるのが一般的ですから、福井在来に限らず全国で栽培されているソバの多くは麺線にした時にいかに美味しく食べられるかを研究し改良されてきています。加えて石臼製粉。粘りのある品種をさらに粘りを引き出す挽き方で製粉することによって十割蕎麦も打てるようになります。しかしそれが料理に使用するときには逆効果になる時があります。
例えば、蕎麦粉のピタパンやパンドカンパーニュは、表面カリカリ中もっちりで香ばしくて美味しかった。これは福井在来種の粘りと石臼で挽く効果によって独特の食感に仕上がっています。
一方、自家製ベーコンを使ったガレットは生地のパリパリ感がアクセントとなる料理です。これに同じようなそば粉を使うと生地が餅のような食感になってしまいガレットとしては満足のいくものができません。
前菜のそばがきもそうです。
そばがきにガレットの粉を使うとサラッとした口どけがなく、もそもそと口に残るような感じで色味も良くない。お皿に盛った時の大きさや配色など全体のバランスも料理の美味しさだと思います。
ですから、どういう料理かを知ってどのようなそば粉が適するかを提案できるかどうかが重要なんだと思いました。そういう意味では、料理は素材を作るプロと料理するプロが共に知恵を出し合っていかないといいモノができない。そして素材のプロでも、ある程度の料理の知識を持っていないと提案できないし分からないと思いました。
北野シェフ、今回は色々と大変勉強させていただきました。
ありがとうございました!
残念ながら、「ル・リアン」は2018年に閉店しましたが、その革新的な料理と地元食材への情熱は、多くの人々の記憶に刻まれています。