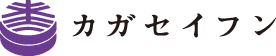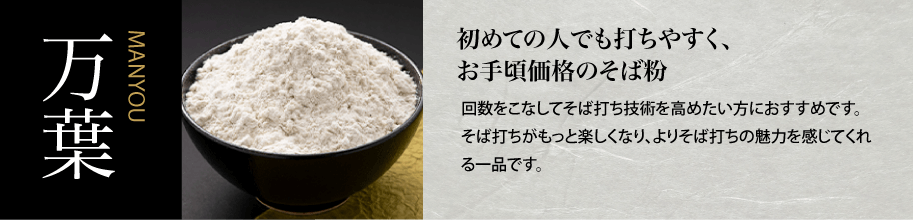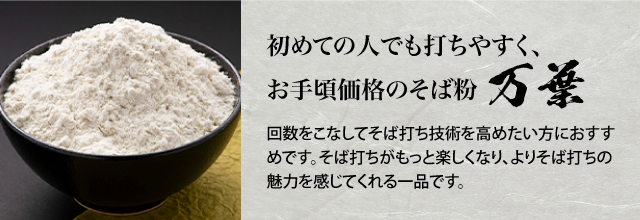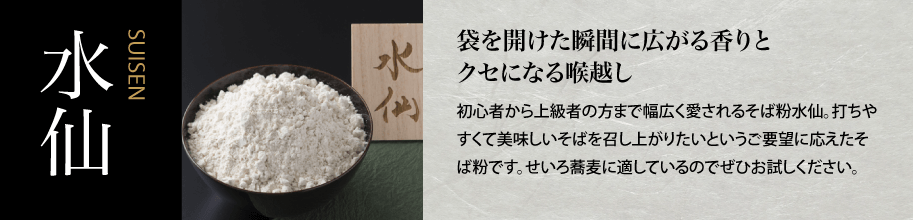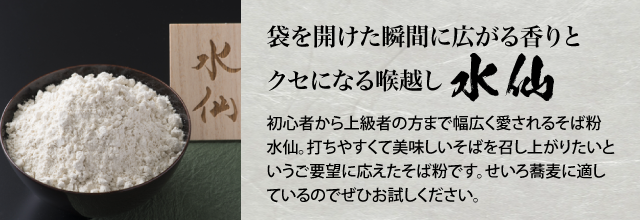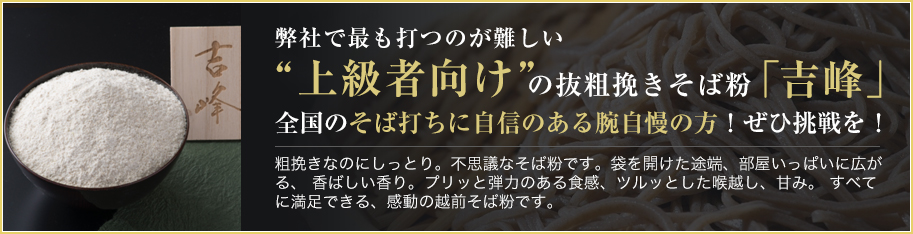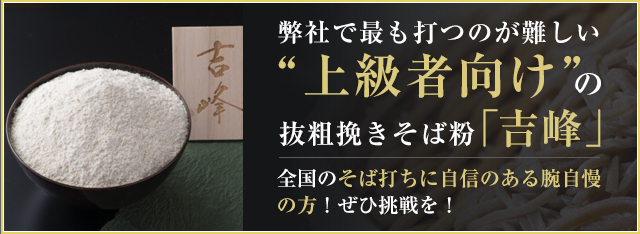カガセイフンの石臼
お客様に満足していただくために
そば粉作りに欠かせない石臼は
私たちの大切なパートナーです。
お客様に満足していただくために
そば粉作りに欠かせない石臼は
私たちの大切なパートナーです。
石を切り出してから
約20年寝かせる理由

石臼は20年寝かせて初めて一人前の石臼になる――その理由は石に含まれる水分量にあります。
切り出したばかりの石は水分を含んでいるため、そのまま使うと年数の経過とともに水分が抜け
ていき、歪みが生じます。そうなると上下の臼が嚙み合わなくなり、次第に粉が挽けなくなって
しまいます。
石臼は一回でも歪んでしまうと成型もできず、摺り合わせることも非常に難しくなります。
一人前の石臼にするには、まずは石を寝かせて水分を抜き、歪みを出しきってから成型します。
石の歪みを出しきらせる時間が約20年。この時間を経て独特の溝をつけると100年、200年と
使い続けられる石臼になります。
最古で200年を
超えるものがある
最古で
200年を超えるものがある
当社の石臼は、古いもので創業当時の石臼(100年以上前)から3代目が使用していた石臼
(現在まで約80年間使用)、3代目が4代目へ残した石臼(現在まで約60年間使用)、そし
て4代目が残した石臼(現在まで約40年間使用)、そのすべてを現在でも現役で使っています。
同じ産地で産出された石ですが古いものほど石のキメが細かいので、年代物の石臼を使うこと
で挽き上りがとてもなめらかでしっとりとしたそば粉が得られます。
また年月を負うごとに石の目(溝)が減って石臼の高さが低くなり、重量も軽くなってきます。
その都度、私たちは重さを足してこれまでと変わらない条件で製粉することを心がけております。
先代が今に残す福井で採れた小和清水石臼は、小粒で実の詰まった福井県産玄そばを挽くにはとても
適しており、この石臼だからこそ、うまみ、風味たっぷりお越前のそば粉を挽くことができるのです。
私たちはこれからもこの石臼と石臼で挽くそば粉を大切にしていきたいと考えています。先代から伝わる
「石臼挽きへのこだわり」と「感謝の気持ち」を込めて越前そば粉をお届けします。
石臼挽きのそば粉の実力
越前福井のミネラルたっぷりな水と 福井在来種玄そば素材のおいしさを引き出す石臼により、明治10年創業の粉奈商時代より140余年末吉の粉奈屋が続けてきたそば粉づくりです。
工場内は品質の均一化を測るための設備は一切ございません。越前福井で採れたソバを自然のままに少しでも良い状態で製粉するよう努めているので、産地の違いはそのままそば粉へ伝わります。工場を市街地から離れた場所に移築したのも「より自然に近い環境でそば粉が挽けるように」という強い思いがあったからです。
気温・湿度・天気などの環境が変われば当然そば粉の仕上がりも違ってまいります。福井県内でも原料の産地によって特色や特徴があるため、毎日、全く同じ質のそば粉になることはありません。夏の暑い時期には、工場内を涼しく保つので私たちは温かい格好で作業し、冬の寒い時期には、工場内の乾燥を防ぎ湿度を保ちます。
挽きたてのそば粉は手でギュッと握り締めた時の触感がしっとりとしており、握った時の手の形がそのまま残ります。そば粉の水分も14~16%ほど残っていますから、水回し(加水)の工程でそば粉と水がうまく混ざり合います。加水した瞬間に立ち上ってくるそばの香りはたまりません。
ロール製粉の良し悪し
そばの製粉方式には【石臼挽き】と【ロール挽き】、今はあまり採用されませんが【胴挽き】という方法があります。
【ロール製粉】は、2つの重なったローラーを内側に引き込むように高速回転させ、ローラーに刻んだ溝で潰すように製粉していきます。粉自体の粘りは生まれにくく、非常に摩擦が大きいために熱を帯びてしまいその時点で香りと味わいが損なわれてしまいます(「粉が焼ける」と表現します)。ソバが加熱されると、香りが飛び、水分が奪われ、パサパサで粘りの無い粉になってしまい、手打ちで蕎麦を打つには向きません。
しかし近年、ロール製粉機の品質向上にあたり、夏場の暑い時期以外は「粉が焼ける」という現象は起こりにくくなりました。この製粉方法の大きな特徴は、1番粉、2番粉、3番粉の挽き分けができるという点です。これによって、一般のお客様はもちろんお蕎麦屋さんの好みに合わせた幅広いニーズに応えることが可能となりました。
【1番粉】
ソバの実の中心部分にあたる純白のそば粉で、透き通ったのど越しの良い麺に仕上がります。花粉(打ち粉)や更科粉(御膳粉)、韓国冷麺用粉として使われ、柚子や抹茶を加えて変わり蕎麦を打つ場合もこのタイプのそば粉です。香りは弱いのですが、甘みがありでんぷん質主体のサラサラとした触感です。
【2番粉】
ソバの中層部分にあたる褐色のそば粉で、ほのかな甘みと香りを持ち合わせています。粒子が非常に細かいので製麺するとツルッとしたのど越しを感じられます。韓国冷麺・製菓用粉としても適しています。1番粉よりも茶色がハッキリ出ますので、このタイプのそば粉を好むお店もあります。
【3番粉】
ソバの実の外側部分にあたる茶褐色の甘皮粉あるいは皮粉です。皮ぎしに栄養が詰まっていて、色が濃く香りも強いのが特徴です。そばクレープ・ガレットなどのお菓子に使っていただくと良いですし、ご使用のそば粉に添加することで香りを高める助けをします。
絶えた技術
もう新しい石臼は作られない
福井産の石を使った石臼づくり。
実はその技術を持った最後の職人さん(清水正生さん)は他界され、その石臼作りの技術が絶えてしまいました。つまりもう新しく作ることができないのです。
しかし、カガセイフンには100年以上受け継がれてきた石臼と、清水さんや先代の助言によって教え込まれた目立ての技術があります。
カガセイフンには清水さんの作った石臼が数台寝かせている状態で、その出番を待っています。カガセイフンが目立ての技術を持つ限り、これからも福井原産の石臼挽きそば粉を提供いたします。ご安心ください。